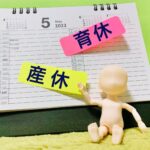出産・育児・復職に関する手続きと給付金の全体像④(最終回)~育児休業を終えて職場復帰するときに~

これまで3回にわたりご案内して来ました「出産・育児・復職に関する手続きと給付金の全体像」シリーズ。今回は最終回として、育児休業を終えて職場復帰する際の制度や給付金、社会保険料の特例措置についてご紹介します。
従業員が育児と仕事を両立しながら安心して働き続けられるよう、さまざまな支援制度が整備されています。今回は、「復帰後の働き方を支える制度」「受け取れる給付金」「社会保険料の特例措置」の3つのテーマに分けて、各制度の内容をご案内します。
「出産・育児・復職に関する手続きと給付金の全体像」ここまでのシリーズはこちら
1.復帰後の柔軟な働き方を支える制度
育児・介護休業法に基づき、仕事と育児の両立を支援する多様な働き方を支える制度の整備が進んでいます。
(1) 短時間勤務制度の義務化
短時間勤務制度とは、育児休業をしていない従業員の所定労働時間を短縮する措置をいいます。3歳未満の子を養育する従業員から申出があった場合、会社は所定労働時間を原則6時間とすることが義務付けられています。業務内容や実施体制などにより短時間勤務が難しい場合には、代替措置も認められています。代替措置は「育児休業に準ずる措置」「始業時刻の変更等」に加え、令和7年4月の法改正では「テレワーク」が選択肢に追加されました。
(2) その他に、小学校入学前の子を養育する従業員は、申し出により以下のような働く時間の調整措置も利用できます。
• 所定外労働の制限(残業免除)
• 時間外労働の制限(月24時間、年150時間まで)
• 深夜業の制限:
(※ただし対象外となる従業員など、一部例外はあります)
子育てや介護と仕事の両立、働き易い就業環境を促進する「育児・介護休業法」の最新情報は、こちらで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
2.受け取れる給付金 ~育児期を経済的に支援する制度~
育児休業から職場復帰した後に、勤務時間短縮により賃金が下がった場合、一定の条件を満たせば雇用保険から給付金が支給されます。経済的不安の軽減につながる制度です。
育児時短就業給付金
2歳未満の子を「育児」するために所定労働時間を短くして勤務(「時短就業」)して、賃金が下がった場合に支給される給付金です。同じく令和7年4月に新設されました。
(1)支給対象者(受給資格、以下2点を満たす方)
- 2歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者。
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した方。または、育児時短就業開始日前の2年間に、賃金支払日数が11日以上(もしくは労働時間が80時間以上)ある月が12か月以上あること。
(その他に、「月の初日から末日まで被保険者である月」「所定労働時間を短縮して就業した期間がある月」など、各月ごとの支給要件もあります)
(参考 >>厚労省ガイド「育児時短就業給付金を創設しました」
(2)支給期間と支給額
- 支給期間は原則として、育児時短就業を開始した月から、子が2歳に達する日(誕生日の前日)までの各暦月が対象となります。(支給期間内に、産前産後休業や育児休業を開始した際など、対象外になるケースがあります)
- 支給額は、育児時短就業中の各月の賃金額の10%が原則です。(ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が「育児時短就業開始時の賃金(*)」を上回らないよう、支給率が調整されます。
(*)「育児時短就業開始時の賃金」とは、その子にかかる時短勤務を開始する前の直近6か月間の賃金総額をもとに算出される月額です。
3.社会保険料を優遇する特例措置
職場復帰後に休業前により賃金が下がった場合に、社会保険では将来の年金額に配慮した特例措置などが用意されています。
(1)社会保険料の軽減(育児休業等終了時報酬月額変更届)
- 育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)終了の際、満3歳未満の子を養育している被保険者が対象です。
- 育児休業終了後に賃金が下がり、これまでの標準報酬月額と1等級以上の差がある場合、(「随時改定」に該当しないケースでも)標準報酬月額が改定されます。負担する保険料を、速やかに育児休業後の実際の報酬に応じた額とする措置です。
- 具体的には、育児休業終了日の翌日が属する月以降の3か月間の報酬を平均し、4か月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
(2) 将来の年金額への配慮(養育期間標準報酬月額のみなし措置)
- 満3歳未満の子を養育する期間中に、標準報酬月額が養育前より下がった場合に、「養育開始月の前月の標準報酬月額」をもとに年金額を計算する特例(「みなし措置」)です。
- 社会保険料の負担は実際の報酬に応じた額である一方で、年金額は養育開始前の標準報酬月額をもとに計算されますので、将来の年金額をできるだけ減少させない配慮措置といえます。
- 対象期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳の誕生日を迎える月の前月までです。
(なお社会保険料の特例は、2で記載した「育児時短就業給付金」と異なり、必ずしも時短就業している必要はありません)
📄 関連資料:無料ダウンロードできます!
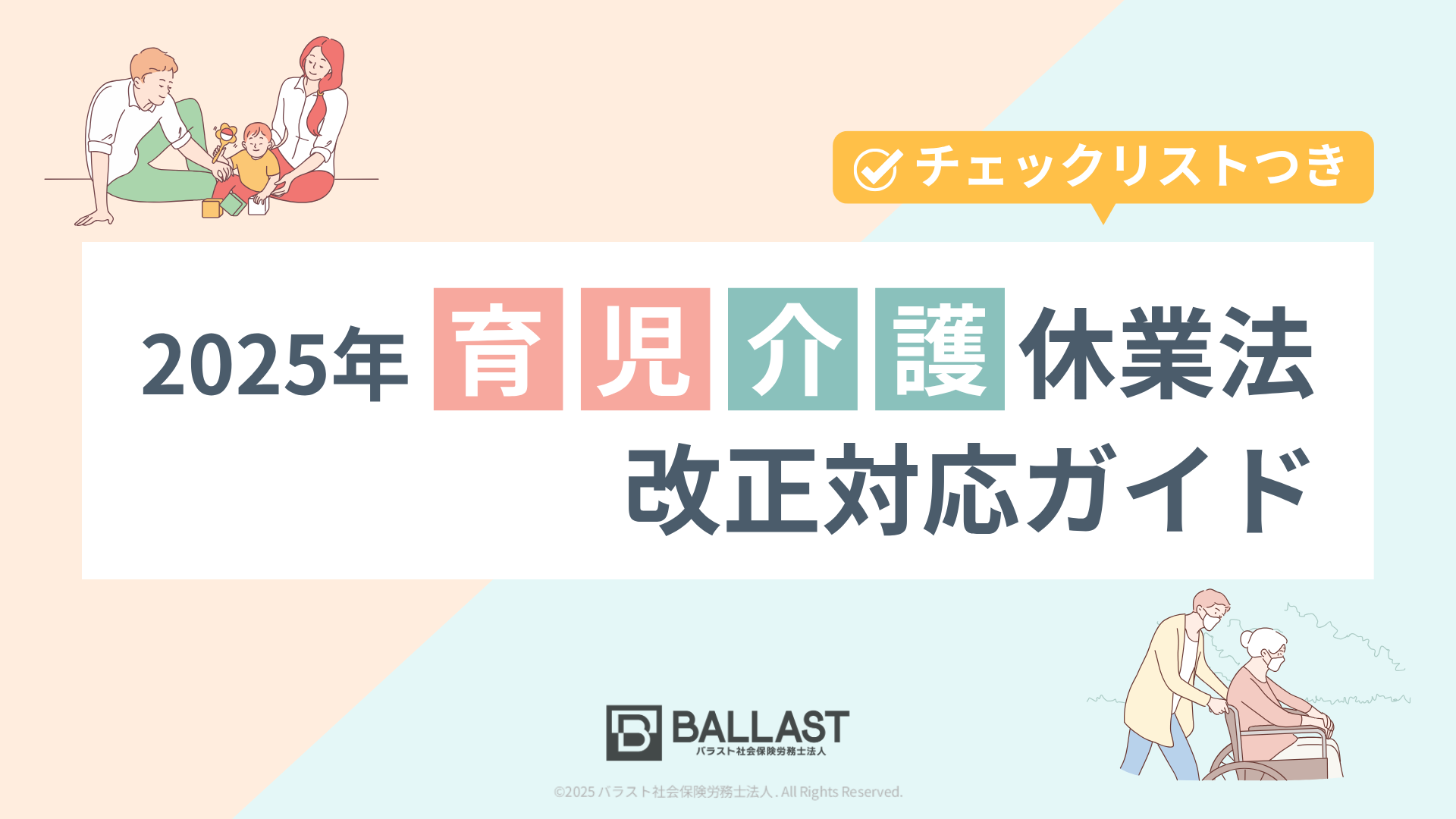 「2025年育児・介護休業法 改正対応ガイド」
「2025年育児・介護休業法 改正対応ガイド」
育児・介護をめぐる法改正の要点やチェックリストを一冊にまとめました。
👉 資料ダウンロードはこちら(メルマガ登録無料)
4.まとめ
出産や育児にかかる支援制度を会社として整え、従業員の仕事と家庭の両立につながる環境づくりは、今後ますます大切な取り組みになっていくと言えるでしょう。
令和7年4月の育児・介護休業法改正による「働き方支援制度の拡充」、それらに連動した雇用保険の「受け取れる給付金の新設」、従来からの「社会保険制度の特例措置」など、従業員が安心して働き続けられる環境を支える施策が進んでいます。ぜひ積極的に活用し、誰もが働きやすい職場づくりにつなげていただければ幸いです。 「うちでも育児や介護にあたる従業員のサポートを見直してみようかな」と感じたら、この機会にチェックしてみてください。東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、10名以上のスタッフが在籍するチームワークの良い事務所です。貴社の課題など、1度お気軽にお寄せください。(鵜頭)
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!
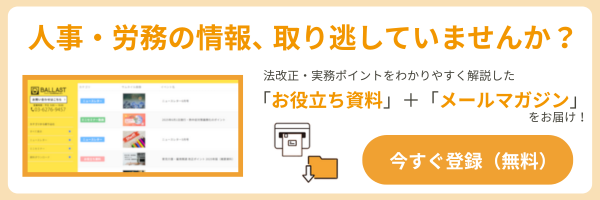
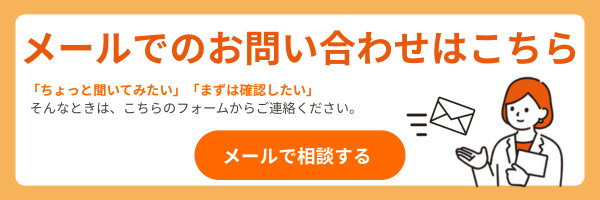

御社の悩み、
無料で相談してみませんか?
無料相談を予約する

執筆
鵜頭 克明
明治大学法学部卒。事務機販売会社に30年余り勤務。ソフトウェア企画部門で製品戦略やサポート体制構築に従事。その後、管理部門で取引先との開発委託契約や派遣先管理に関わる中、労働者を取り巻く環境に関心を深め、2023年社労士試験に合格。2024年8月にバラスト社会保険労務士法人へ入社。手続き・給与計算、助成金申請や就業規則改正などを担当し始めている。落ち着いた対応とロジカルな思考で、誠実なサポートに努めている。