社会保険上の扶養について再確認してみませんか②
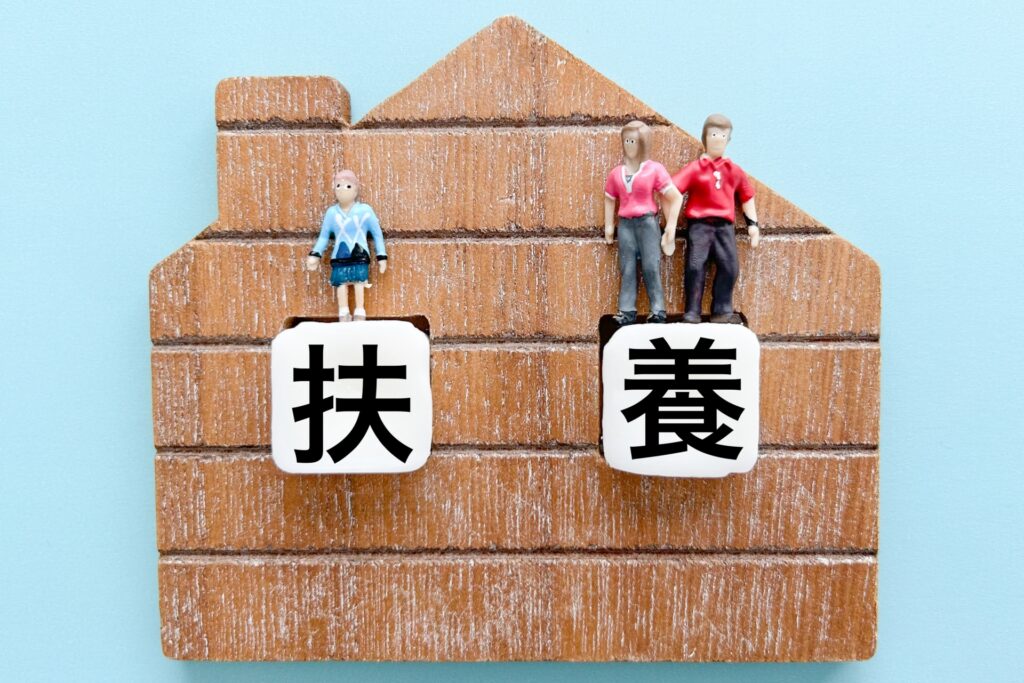
社会保険上の扶養について再確認してみませんか②
1.はじめに
こんにちは。荻窪のバラスト社会保険労務士法人の髙山です。
新年度が始まり、入社や異動などで家族構成や働き方に変化が生じやすいこの時期。今回は、実務でも誤解が多い「社会保険の扶養」について、基本から改めて確認してみたいと思います。
2.社会保険の「扶養」とは?
「扶養」というと税金の話を思い浮かべる方も多いですが、今回は社会保険、特に健康保険と年金保険における扶養制度についてお話しします。
社会保険上の扶養に該当すると、例えば以下のようなメリットがあります。
- 被扶養者が保険料を支払うことなく健康保険に加入できる
- 医療費の窓口負担が3割になるなどの給付を受けられる
- 介護保険料や国民年金保険料の支払いが不要になる場合がある
こうしたメリットは、扶養に「入れる側(被保険者)」だけでなく「入る側(被扶養者)」にとっても非常に大きなものです。
ただし、これは申請して認定を受けることで初めて有効になります。つまり、黙っていては扶養にならない、という点が非常に重要です。
3.社会保険の扶養に入れるための要件
では、どのような条件を満たせば「社会保険の扶養」に入れるのでしょうか?主なポイントは以下の3つです。
① 対象者が親族であること
- 原則、3親等以内の親族が対象です。
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。
② 所得(年収)要件を満たしていること
- 年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)が基本ライン。
- かつ、被保険者の収入の半分未満であること。
- 同居か別居かによって「収入比較の対象」や「仕送りの有無」などが異なります。
③ 生計維持関係があること
- 別居している場合:定期的な仕送りがあり、それで生活していることが必要。
- 同居している場合:収入要件を満たしていれば比較的認定されやすい。
4.よくある注意点と誤解
- 「申請しなければ自動的に扶養になる」は誤り
被扶養者に該当していても、手続きをしなければ制度上は扶養と認められません。
- 収入の「見込み」で判断される
パートやアルバイトで収入が月々変動する場合でも、「今後1年間の見込み」で判定されます。
雇用契約書や過去の給与実績をもとに判断されるため、入社直後や収入が安定しない場合は注意が必要です。
- 被扶養者異動届を忘れずに
収入増、就職、結婚・離婚、死亡など、家族状況が変わったときは速やかに「被扶養者異動届」の提出が必要です。
5.社会保険扶養の実務ポイント
- 健康保険には扶養の制度があるが、国民健康保険にはない
- ただし、厚生年金には扶養の制度がない(その代わり、配偶者は「第3号被保険者」として国民年金に加入できる)
6.まとめ
社会保険の扶養は、知っているかどうかで損得が大きく変わる制度です。
とりわけ人事・労務担当者にとっては、従業員の家族情報を正確に把握し、適切に扶養の判断をすることが求められます。
判断が難しいケース(同居/別居の要件や仕送りの実態など)も多々ありますので、不安があれば専門家への相談をおすすめいたします。
当法人でも扶養認定に関するご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!
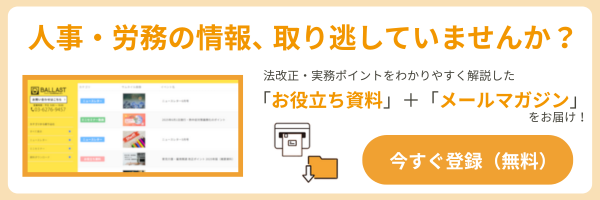
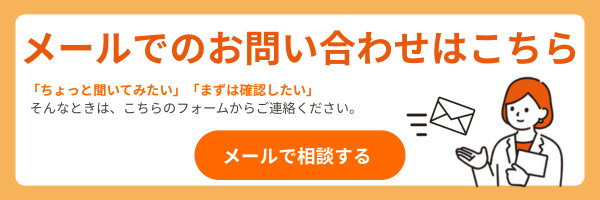

御社の悩み、
無料で相談してみませんか?
無料相談を予約する

執筆
髙山 暁
前職は速記士として活動。保険知識の不足を実感したことと、経営者・労働者が気を配りにくい部分を支えたいと思ったことから、社労士を志し、2021年社労士試験に合格。2024年にバラスト社会保険労務士法人へ入社し、社会保険手続きや日常的な労務対応を数多く担当。初めて顧問先のお手続きを完了した経験を糧に、誠実かつ穏やかな対応で信頼を得ている。




