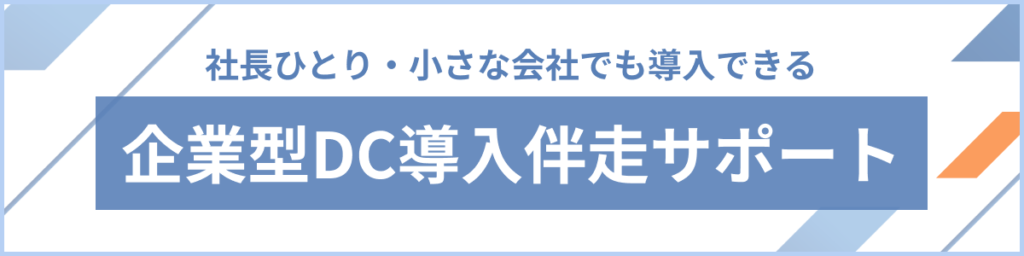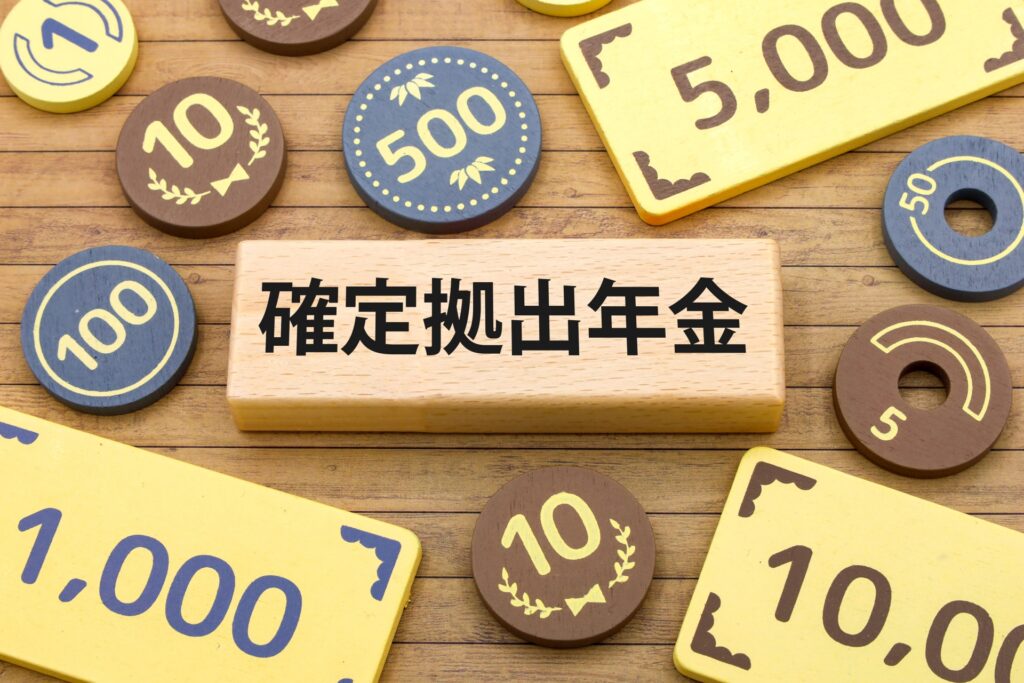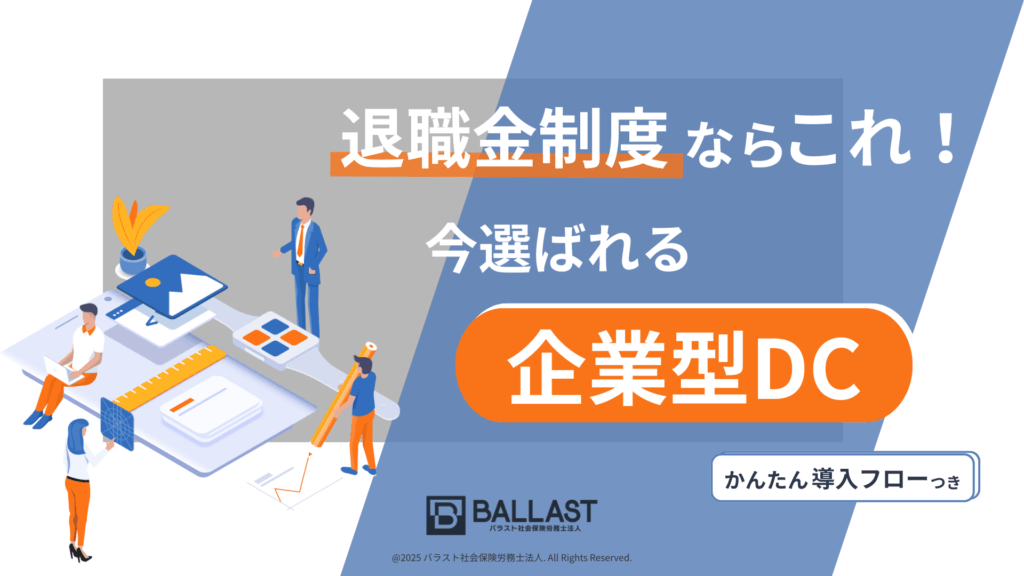「退職金制度、どれにする?」〜今あらためて考えたい4つの選択肢〜(1/4)

近年、「年金だけでは老後の生活が不安」という声を耳にする機会が増えています。働く人にとっては、将来の安心につながる退職金制度の充実が大きな関心事になっていますし、企業にとっても人材の確保・定着に欠かせない要素となっています。
しかし一口に退職金制度といっても仕組みはさまざまで、「何を選べばよいのか分からない」という経営者の声も少なくありません。
そこで今回は、企業型DC(確定拠出年金)に注目しながら、企業における退職金制度の主な4つの種類と、制度設計を考える際のポイントについてお話しします。(全4回)
目次
1.退職金制度の4つのパターン
① 古き良き「社内積立型退職金制度」
多くの人がイメージするのはこれ。
在職年数や最終月給をもとに支給額を計算し、退職理由によって減額などがあるスタイル。
ただしこれ、制度を維持するのは実はかなり大変です。
退職者が重なる時期(例:団塊世代の定年)には一気に多額の支払いが発生。
社内で資金を留保し続けるのは、特に中小企業では大きな負担になります。
賞与のように「業績次第で出さない」というわけにもいかず、給与と同じ性質を持つため、支払い義務が重くのしかかります。
② 中退共(中小企業退職金共済制度)
国が運営する中小企業向けの外部積立制度。
会社が毎月一定額を掛金として納付し、退職後は従業員本人が自分で請求して受け取ります。
- 掛金は1人あたり月額5,000円〜30,000円の範囲で選択可能
- 会社負担で全額損金扱い(節税メリットあり)
- 退職金は中退共から直接支払われ、会社のキャッシュフローに左右されない
中小企業にとっては手間も少なく、導入しやすい制度です。
③ 確定給付年金(DB)
こちらは「働いたら○○円もらえる」と給付額を先に決めておくスタイル。
運用は金融機関に任せる形が多く、不足すれば会社が補填。
最近では「はぐくみ基金」のように、DB制度を中小企業でも導入しやすくした商品も登場しています。
この制度は、会社の負担額と従業員の受け取る額がほぼ一致するように設計されており、運用失敗のリスクを抑えた“安心型”の仕組みです。
③ 確定拠出年金(企業型DC)
今、注目を集めているのがこの制度。
別名企業型DC(Defined Contribution)、もしくは日本版401Kとも呼ばれます。
- 会社が毎月一定額(例:5,000円〜)を従業員ごとの口座に拠出
- 拠出したお金は従業員自身が運用(定期預金や投資信託など)
- 60歳以降に、運用成果に応じた金額を年金または一時金として受け取り
つまり、会社は積立だけを担当し、将来いくらもらえるかは自己責任。
これにより、会社にとっては将来の支払いリスクがなく、従業員にとっては“自分のためのお金”として自覚が持てる制度です。
2.企業型DCは「退職金×節税×採用強化」の切り札
企業型DCについては、次回詳しくお話しますが、導入企業が増えている理由は以下の通りです。
- 法人税・社会保険料の節税効果
- 退職金制度としての明確性と平準化
- 福利厚生としての魅力向上 → 採用力・定着力アップ
「ちょっと怪しい制度じゃないの?」と感じた方もいるかもしれませんが、ちゃんと制度設計すれば、社員にも会社にもメリットが大きい仕組みなんです。
まとめ:退職金制度、選択肢は一つじゃない
いまや「退職金制度はあって当たり前」ではなく、「自社に合った仕組みを設計する時代」です。
企業の財務状況、従業員のライフプラン、税務メリットなどを総合的に考えて、適切な選択をしていきましょう。
次回は、今回ご紹介した中でも特に注目されている企業型DC(確定拠出年金)について詳しくご紹介します。
バラスト社会保険労務士法人では、退職金制度の設計や、企業型DC導入支援も承っています。
「そろそろ制度を見直したい」「制度を整備したいけど何から始めればいいかわからない」という企業様、まずはお気軽にご相談ください。
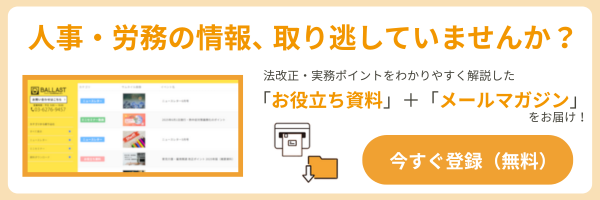
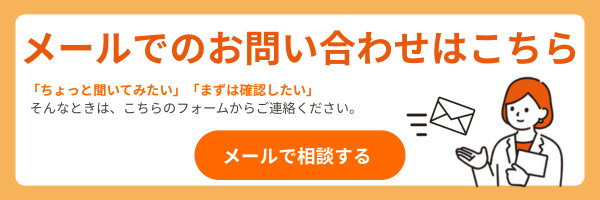

御社の悩み、
無料で相談してみませんか?
無料相談を予約する

執筆
平野 麻希子
明治大学文学部卒業、関東ITソフトウェア健康保険組合にて健康保険の運営に携わる。人を雇用する事に興味を持ち、社会保険労務士となる。2011年千葉県野田市にて平野麻希子社会保険労務士事務所開業。2024年バラスト社会保険労務士法人に参画。流山事業所所長。中小企業のサポート経験を活かし、助成金や社会保険の寄り添ったサポートを得意としている。