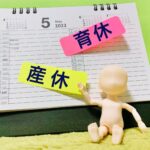出産・育児・復職に関する手続きと給付金の全体像② ~休業前~

前回のコラムで出産・育児・復職に関する手続きと給付金の全体像について取り上げました。
今回は、これらの制度を利用するため「休業前」に企業が行っておくべきことについて解説します。
前回コラム 全体像はこちら
目次
1.就業規則の整備
産前産後休業や育児休業などの制度は、法律に基づき労働者に当然に認められる権利です。とはいえ、実際の運用においては、制度の内容や申出方法、社内手続き等を明確にしておくことが重要であり、就業規則や育児・介護休業規程への記載が強く推奨されます。
特に、育児・介護休業法の改正により、事業主は3歳未満の子を育てる労働者に対して、柔軟な働き方に関する措置を2つ以上講じる義務があります。短時間勤務制度や時差出勤、テレワーク制度など、会社としてどの措置を講じるかは自由ですが、措置の内容や対象者、申出手続などを社内規程として整備しておかないと、義務を履行しているとは見なされません。
また、過去に作成した就業規則や規程の内容が現在の法制度に即していないケースもあります。育児休業制度は近年改正が頻繁に行われている分野であるため、この機会に制度の流れや手続きの見直しを行い、社内での周知・運用を確実なものとすることが大切です。
記載内容については、厚生労働省が公表しているモデル規程を参考にできますが、個々の企業の運用に合わせた整備が求められます。
2.労使協定の締結 ※任意(除外対象の設定)
労使協定について述べる前に、育児休業の取得条件を以下のとおり簡単に申し上げます。
〔育児休業取得条件〕
・1歳に満たない子を養育すること
・期間を定めて雇用される者は、申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
※日々雇い入れられる者は除かれます。
上記により、条件を満たせば雇い入れ直後であっても育児休業を取得することが可能です。そのため、企業としては、採用したばかりの従業員がすぐに育児休業に入ることにより、人員体制や業務運営に課題を感じる場面もあるかもしれません。
こうした場合に備え、法律では一定の要件に該当する労働者を対象から除外できる「労使協定」の制度が設けられています。
ただし、この除外はあくまで例外的な運用であり、制度の趣旨(育児と就労の両立支援)に十分配慮した慎重な対応が求められます。
〔労使協定締結によって追加できる条件〕
・雇い入れ期間が1年未満でないこと
・育児休業申出の日から1年以内(1歳6か月まで及び2歳までの育児休業をする場合には、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかでないこと
・1週間の所定労働日数が2日以下でないこと
なお、産前産後休業にはこのような除外規定はありません。混同しないように注意しましょう。
3.制度の周知と意向確認 ※2022年4月1日から施行
育児休業は、労働者本人の申出により取得できる制度ですが、申出がなければ企業側に取得させる義務は発生しません。
しかし、制度そのものを知らなかったために申出ができなかったというケースも現実に起きていたことから、この点を改善する目的で、令和4年4月より「制度の周知と意向確認」が事業主の義務とされました。
制度としてはすでに義務化されている内容ではありますが、運用が形骸化していたり、対象者の把握が不十分であったりするケースも散見されます。対象となる労働者が出た場合には、確実に周知・意向確認を行うよう注意が必要です。
〔周知事項〕
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
〔個別周知・意向確認の方法〕
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。
また、両親がともに育児休業を取得する際、条件を満たせば手取り額がおよそ100%になる「出生後休業支援給付金」が支給される可能性があります。育児休業取得の申出があった場合、配偶者の状況も確認するようにしましょう。
申出を行う労働者が女性の場合、育児休業の開始前に産前産後休業を挟む形となるケースが多く見られます。
特に、産後休業は法律により、産後8週間は原則として就業させてはならない「就業禁止期間」とされており、企業側も制度を正しく理解し、確実に対応する必要があります。
一方で、産前休業は本人の申出によって取得の有無が決まります。
そのため、出産予定日をもとに「産前休業 → 産後休業 → 育児休業」と続く可能性があることを前提に、申出時期や手続の流れをあらかじめ説明しておくと安心です。
4.柔軟な働き方を実現するための措置等 ※2025年10月1日から施行(新設義務)
2025年10月1日から、柔軟な働き方を実現するための措置等が新しく義務化されます。簡単に内容を申し上げると次のとおりとなります。
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が柔軟に働くことができるよう、後述する「企業が選択して講ずべき措置」から2つ以上を企業が選択し、労働者に選んでもらうというものになっています。10月の改正に間に合うよう、前もって検討しておくことをお勧めします。
〔企業が選択して講ずべき措置 ※この中から2つ以上を選択〕
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
また、企業は選択した措置を労働者が選択できるようにするため、個別の周知・意向確認を行うことが義務づけられることになります。
〔周知時期〕
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
〔周知事項〕
①事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容
②対象措置の申出
③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
〔個別周知・意向確認の方法〕
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。
育児休業時と異なり、労働者から申出があってから周知・意向確認をするのではない点に注意が必要です。労働者に3歳未満の子がいるかどうかを把握するのは難しい側面もあるため、定期的に情報を収集するようにしましょう。
5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 ※2025年10月1日から施行(新設義務)
2025年10月1日から、事業主には、仕事と育児の両立を図るための働き方について、対象となる労働者に個別に意向を聴取し、その内容に配慮することが義務付けられます。
これは、さきに述べた「柔軟な働き方に関する措置義務」とは別に、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応を促すための制度です。
〔意向聴取の時期〕
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
〔聴取内容〕
①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
〔意向聴取の方法〕
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ
なお、この制度は、労働者の希望をすべて実現することを義務付けるものではありません。
あくまで、本人の意向を丁寧に聴き取ったうえで、業務の状況や職場全体との調整も踏まえて、可能な範囲で配慮することが求められています。
一方的に希望を拒否したり、聴取そのものを省略したりすることは制度違反となる可能性があるため、やり取りの記録を残しつつ、誠実に対応することが重要です。
📄 関連資料:無料ダウンロードできます!
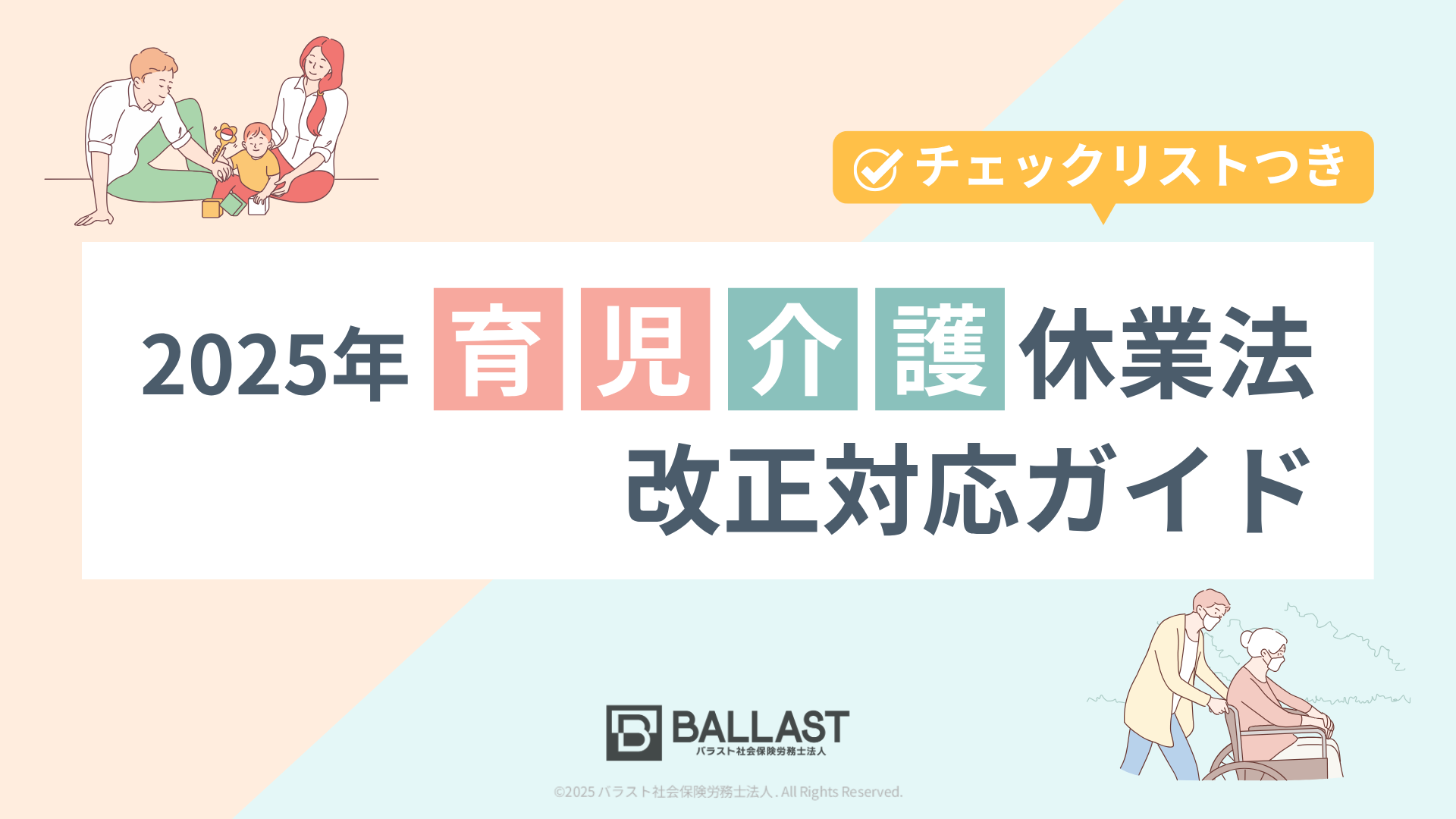 「2025年育児・介護休業法 改正対応ガイド」
「2025年育児・介護休業法 改正対応ガイド」
育児・介護をめぐる法改正の要点やチェックリストを一冊にまとめました。
👉 資料ダウンロードはこちら(メルマガ登録無料)
6.まとめ
出産、育児関係は年々制度が充実し、労働者にとっては大変役立つ一方、人事担当の方にとっては法改正への対応に頭を悩ませるところでもあります。特に、義務づけられている部分への対応は必ず行う必要があるため、「いつ・何を・どうするか」をあらかじめ確認し、漏れなく対応できるようにしておくとよいでしょう。就業規則や労使協定などのように前もって対応しておく必要のあるものもあるため、これを機に確認してみてはいかがでしょうか。
これまで述べてきたように、出産・育児制度関連に漏れなく確実に対応していくのはとても大変なことがお分かりいただけたかと思います。東京都杉並区荻窪で活動している当法人では、出産・育児・復職に関する制度の導入支援や就業規則の整備など、企業のご事情に応じたサポートを行っております。制度対応にお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
次回は、実際に子が生まれた後のことについて取り上げますので、こちらもお読みいただけますと大変うれしく思います。(髙山)
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!
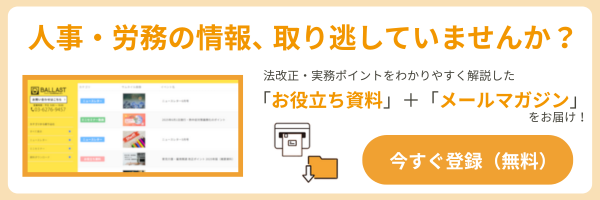
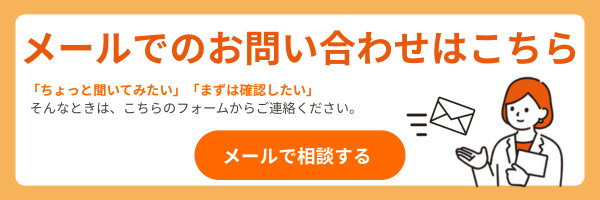

御社の悩み、
無料で相談してみませんか?
無料相談を予約する

執筆
髙山 暁
前職は速記士として活動。保険知識の不足を実感したことと、経営者・労働者が気を配りにくい部分を支えたいと思ったことから、社労士を志し、2021年社労士試験に合格。2024年にバラスト社会保険労務士法人へ入社し、社会保険手続きや日常的な労務対応を数多く担当。初めて顧問先のお手続きを完了した経験を糧に、誠実かつ穏やかな対応で信頼を得ている。