社労士と始める、フレックスタイム制の導入ガイド➀ ~概要~

フレックスタイム制は、多くの企業で使われている働き方です。名前は広く知られていますが、「複雑」「手続きが面倒」というイメージから、実際には活用していない企業も少なくありません 。
実際には、基本ルールを押さえ、正しく整備すれば、シンプルに運用できる制度です。社労士が関わることで、法的要件を満たしながら会社に合った形でスムーズに導入できます。
1.フレックスタイム制の基本ルール
フレックスタイム制は、従業員が自分で始業・終業時刻を選べる仕組みです。仕事と生活の両立を支援し、会社にとっても生産性向上や人材定着につながる便利な制度といえます。
2.制度導入の要件は2つ
フレックスタイム制は、次の2つを押さえれば導入できます。
- 就業規則等に明記する
「始業・終業時刻は従業員が決める」ことをルールとして書きます。
※常時10人未満の事業場は、就業規則の代わりに労働条件通知書や労使協定への記載でも問題ありません。
- 労使協定で決める
誰が対象か、清算期間(※1)はどのくらいか、清算期間の労働時間、1日の労働時間、必要に応じてコアタイム(※2)やフレキシブルタイム(※3)も定めます。また、清算期間を1か月を超えて設定する場合には、労働基準監督署への届出が必要です。
※1 清算期間とは、一定期間(最長3ヶ月)で働くべき労働時間の総枠を定める期間
※2 コアタイムとは、必ず働かなければならない時間
3.フレックスタイム制の賃金精算ルール
通常の労働時間制では、1日8時間・週40時間を超えた時点で時間外労働となり、その都度割増賃金を支払います。
一方、フレックスタイム制では、労働時間の計算を清算期間で行います。そのため、1日や1週間で法定時間を超えても、原則は清算期間の労働時間の総枠内であれば時間外労働にはなりません。総枠を超過した場合は賃金を追加で支払う必要があります。
4.まとめ
会社にとっては、労働時間の効率化や従業員の定着率向上が期待できるフレックスタイム制。その一方で、労働時間管理や賃金計算は通常の制度とは異なるため、正しいルールを理解し、適切に運用することが不可欠です。
次回は、実際に制度を導入する際の制度設計や労使協定について詳しく解説します。
バラスト社労士事務所では、フレックスタイム制の導入に向けてご支援が可能です。東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、総勢10名以上が在籍するチームワークの良い事務所です。ぜひ1度お気軽にご相談ください。(松下)
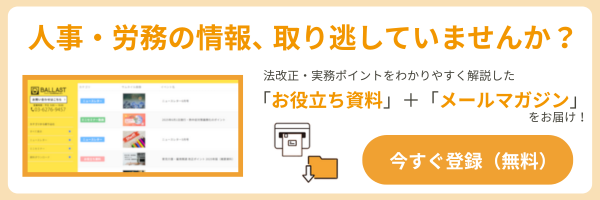
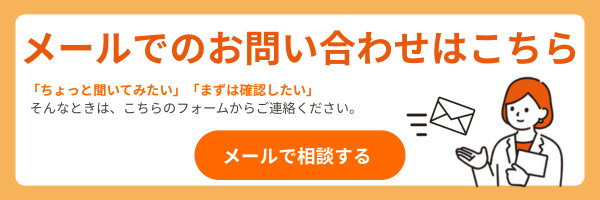

御社の悩み、
無料で相談してみませんか?
無料相談を予約する

執筆
松下 丘
日本大学文理学部卒業 金融機関でライフプランの相談を通じた個人向け保険営業に従事。公的な保険について興味を持ち、社会保険労務士に。2020年バラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)入社。就業規則作成や労働時間制度(フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の相談と導入を数多く対応している。誠実で穏やかな対応に定評がある。野球好き。





