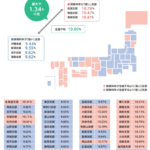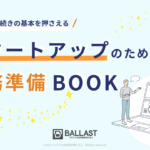「在宅勤務手当」の導入にあたって~「報酬等」に含まれるのか~

コロナ禍を契機に、在宅勤務を始めとするテレワークが急速に普及しました。それに伴い、「在宅勤務手当」を新設する会社も増えてきています。今回は、この手当が社会保険・労働保険料の「報酬等」に含まれるのか、導入時の基本的なガイドラインと合わせご紹介します。
目次
1.「在宅勤務手当」導入にあたっての基本的な考え方
テレワークにより、通信費や光熱費など業務上の費用が発生します。これらをどう負担するかは労使で話し合い、就業規則等で取り決めておくことが望ましいとされています。 社会保険料等の「報酬等」とは、「労働者が労働の対償として受けるもの」であり、通常の生計に充てられるものを含みます。在宅勤務手当が該当するかは、手当の名称ではなく、支給要件や実態に基づき判断されます。
2.「報酬等」として社会保険の算定基礎に含まれるケース
在宅勤務手当が「報酬等」となるのは、労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらない)です。判断基準は、「従業員が在宅勤務のための費用として使わなくても返還不要かどうか」とされています。
◆【報酬となる例】 「定額支給の『渡し切り』手当」(例: 「毎月5,000円を支給する」)
これは、従業員の通常の生計に充てられる収入とみなされます。使い道の限定はなく、労働の対償としての性質を持つため、「報酬等」に含まれ社会保険料の算定基礎となります。
3.「実費弁償」として社会保険の算定基礎から除外できる部分
一方、在宅勤務に伴う「実費弁償」に当たる場合は、「報酬等」には該当しないとされています。在宅勤務にあたり業務遂行に必要な実費を、労働者が立て替え、費用を精算して弁償を受けるケースです。
【実費弁償とされる具体例】
(1) 通信費・電気料金:在宅勤務によって増加した料金は、実費弁償として扱える可能性があります。
<精算方法のポイント>
- 通信費や電気料金など、生活費と一括請求される費用については、実費弁償分の算出方法を就業規則等に明記する必要があるとされています。
◆業務のために使用した部分を計算する方法例(国税庁FAQより引用)
月の在宅勤務日数や自宅の床面積における業務使用割合に、1日の労働時間割合(概ね1/2)を用いて業務使用分を算出する手順が、合理的とされています。
- 従業員が立替払いし、明細等を提出して会社から精算を受ける場合、業務使用分の実費弁償に該当します。
(2) 事務用品・機器の購入費:業務で使用するこれら費用も、実費弁償として扱える可能性があります。
<精算方法のポイント>
- 従業員が立替払いにより購入後、領収証等で精算する場合は実費弁償に当たります。
- 事務用品等物品の所有権は、会社(従業員に「貸与」する形態)であることが原則です。 (所有権が労働者に移転する(「支給」となる)場合は、現物給与として「報酬等」に含めるとされています)
◆参考資料◆ >> 国税庁における在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ
4.まとめ~「報酬等」に含まれるのか~
在宅勤務手当の新設、既存の通勤手当の変更は、社会保険料の改定(随時改定等)対象となる場合があります。
- 実費弁償に当たらない在宅勤務手当(例:渡し切りの定額手当)は、「固定的賃金の変動」となり、随時改定に該当する可能性ある。
- 通勤手当の廃止や支給方式変更(月額から日額など)も同様。
- 1つの手当に「実費弁償分部分」と、「それ以外の部分(報酬となる)」がある場合には、実費弁償分は「報酬等」に含めず、それ以外の部分が「報酬等」に含まれる。
5.導入に向けて
在宅勤務手当の導入に際しては、目的をどう定めるかが大切なポイントと考えられます。
(1) 従業員の経済的負担軽減や福利厚生面を重視し、手当をシンプルにしたい場合
→定額手当(報酬として取り扱う)を導入。社会保険料等増には留意しつつ、運用をシンプルにする。
(2) 業務上の実費を適切に補填したい場合
→実費精算方式(実費弁償扱い)を導入。通信費等の算出基準を決めて、就業規則等に記載する。
今回ご紹介したガイドラインを踏まえると、通信費などの実費精算による手続きの煩雑さを考慮し、従業員に経常的な収入として定額「渡し切り」方式を採用することも1つの考え方かも知れません。合わせて、会社として「在宅勤務を含む多様な働き方を支援する」というメッセージを示すことも検討できるでしょう。また、固定的賃金の増加に伴う給与支給額をトータルで見てみる機会にもなり得そうです。
本コラムの参考資料はこちらです。
>>標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(PDF P15~)
※なお、本コラムでご紹介していませんが、在宅勤務等における労務管理ガイドラインはこちらです。
>> テレワークにおける適切な労務管理のガイドライン(PDF)
東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、10名以上のスタッフが在籍するチームワークの良い事務所です。在宅勤務導入の留意点などを踏まえ、御社の状況等に合わせた手当設計、それらに伴う就業規則改定、社会保険手続き(随時改定等の要否)までトータルでサポートします。貴社の課題など、ぜひ1度お気軽にご相談ください。(鵜頭)
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!
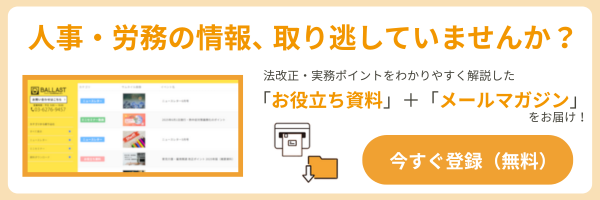
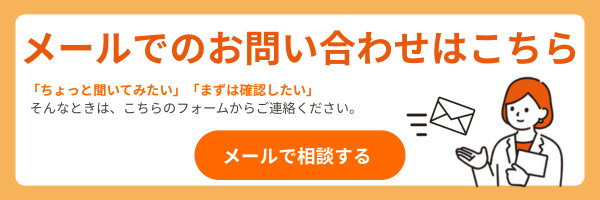

御社の悩み、
無料で相談してみませんか?
無料相談を予約する

執筆
鵜頭 克明
明治大学法学部卒。事務機販売会社に30年余り勤務。ソフトウェア企画部門で製品戦略やサポート体制構築に従事。その後、管理部門で取引先との開発委託契約や派遣先管理に関わる中、労働者を取り巻く環境に関心を深め、2023年社労士試験に合格。2024年8月にバラスト社会保険労務士法人へ入社。手続き・給与計算、助成金申請や就業規則改正などを担当し始めている。落ち着いた対応とロジカルな思考で、誠実なサポートに努めている。